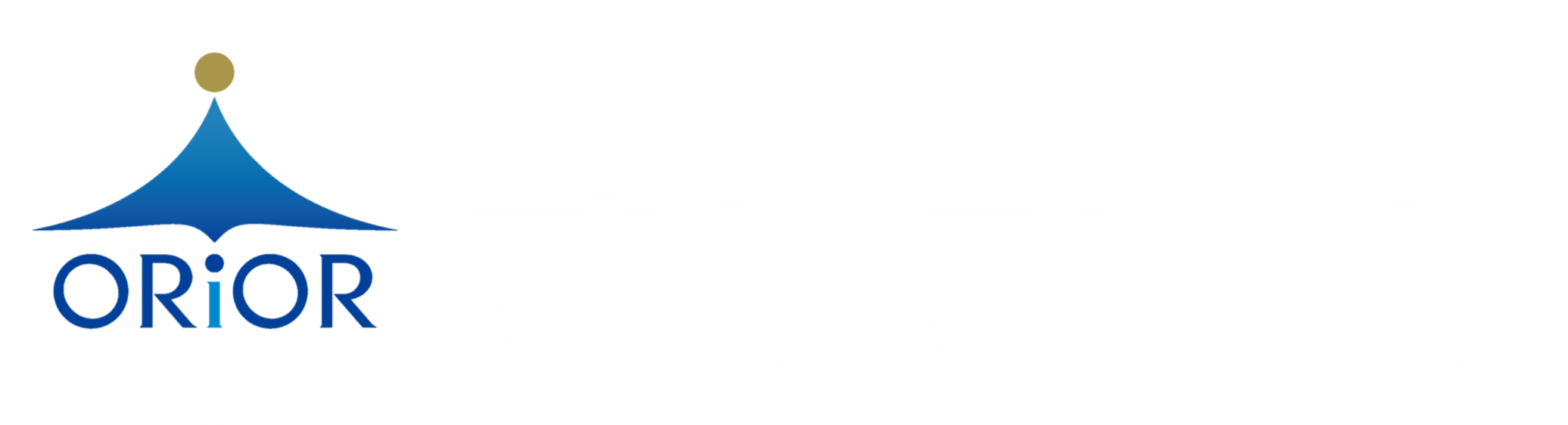「四書五経」とは、儒教において重要な経典として尊重された書物の事を指します。
四書とは,『大学』『論語』『孟子』『中庸』。
五経とは『易経』『詩経』『書経』『礼記』『春秋』の事を言います。
儒学の中心は、はじめは五経だけでしたが、宋代の朱子学が「四書を基本におき、五経も学ぶべき」と言い始め、「四書五経」となり役人や教育に関連する仕事をする人達の学ぶべき書籍となりました。
儒学を学んだの中には賢人偉人も多く輩出され、安井息軒、中江藤樹、貝原益軒、林羅山、伊藤仁斎、荻生徂徠、渋沢栄一など、そうそうたる顔ぶれが日本人儒学者におります。
しかしながら残念なことに、儒学には創始者である孔子の考え方もあり、この世的なことが中心となり過ぎるきらいがあり、無神論国家の代表格でもある中華人民共和国で、人心掌握術として使われている感が否めません。
もともと孔子自体は、霊界などあの世を否定はしておりませんでしたが、さも「あの世などない。霊などない。魂など存在しない。」というように言った様に語られております。
しかし、孔子は明確に否定もせず、肯定もしないと言う態度を取っていたことが、四書を読めば理解できるかと思います。