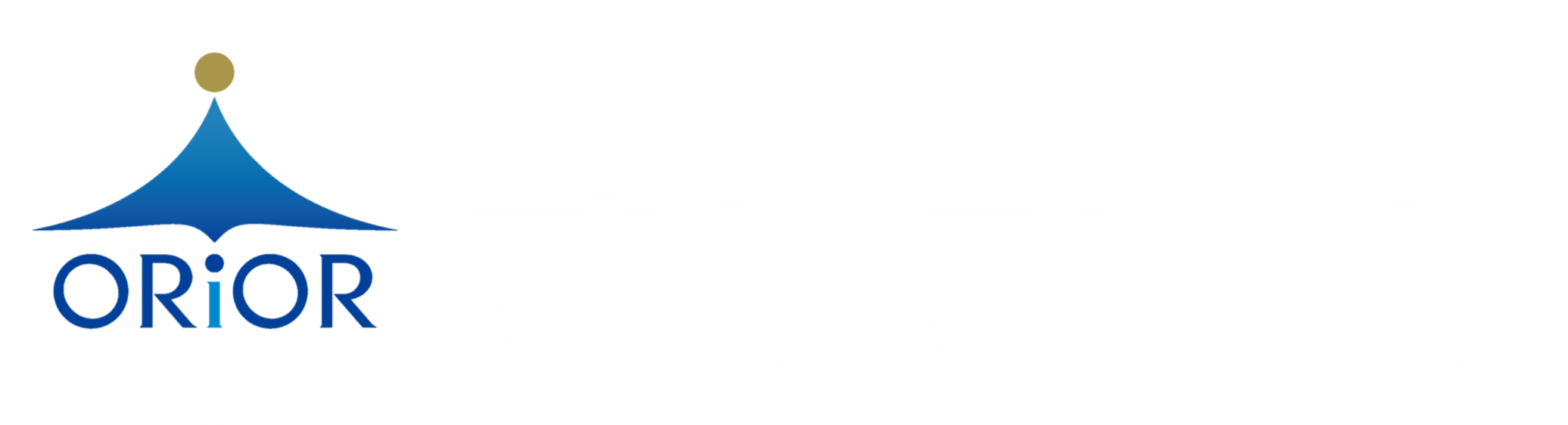講演会やセミナーとかに参加される方はご存知かと思いますが、質疑応答が可能なイベントは、その規模が大きくなればなるほど少なくなります。
それは、聴衆が増えれば増えるほど、予測不能な質問が飛び出す危険性が増すから、主催者側はたまらなく成るからです。
だから講師の中にはスタッフに頼んで「事前に質問内容を私に伝えるように」と用意をしておく方もいらっしゃったりします。
あらかじめ質問内容が分かっていれば、現場でアタフタしなくて済むし、講師もしっかりと答えられるので、聴講者の印象も良くなります。
しかし、こうした事をしているようでは、講師も講義内容も成長しません。
宮本武蔵は晩年になって、様々な武芸者と言われる人達の質問を受けていたそうです。
ある時「私は、木剣では誰にも負けることはないくらいに強い武芸者です。だから真剣でも戦えます。」と自慢してきた人に対して「あなたは強いと言うけれど、世の中には強い人はいくらでもいるんだよ。指南役で教えたりするのは良いけれど、命のやり取りをする真剣での戦いはするものではない。」と諌めたと言われています。
60戦以上の戦いで、無敗の宮本武蔵が「戦いなんて喜んでするべきものではない。」と言うわけです。
要するに「本当の達人になったら、剣さえ持たず、普通の老人のように、淡々として生きていけるといった状態でなければいけないんだ。」という事を言いたいのではないかと思います。
翻って質問を受けない講師で「生の質疑応答を怖がっている内は、木剣で戦っているようなもの。」ですので、本物に達人であればあるほど、生での予期せぬ質問を楽しがります。
それこそが、お釈迦様が弟子たちに教えた「大切な修行の一つ」として、幾度も説法した「対機説法」に繋がっていくわけですね。