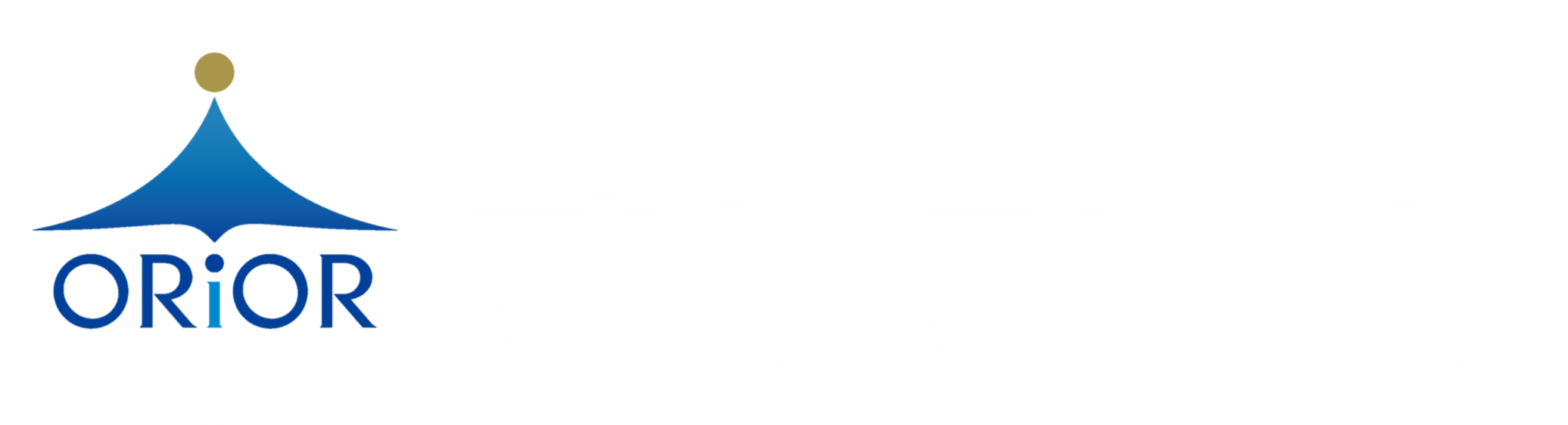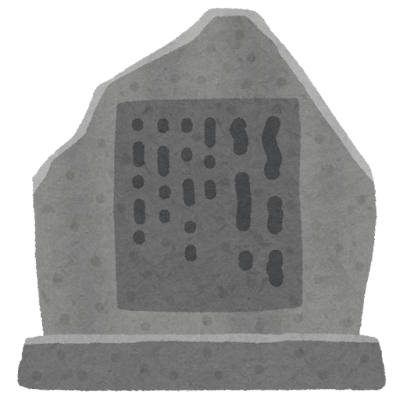日本の文字文化における大きな影響力があった時代として、「白村江の戦い」があげられます。
白村江(はくそんこう、はくすきのえ)の戦いは、663年に朝鮮半島南西部の白村江(現在の錦江河口)で、日本・百済連合軍と唐・新羅連合軍の間で行われた海戦のことです。
この戦いで日本軍は大敗を喫し、百済は滅亡、日本は朝鮮半島への足がかりを失っただけではなく、大陸文化が大波の様に押し寄せて来たのです。
この敗戦を契機に、日本は唐・新羅に対して服従する様な形となり、勢いそれまで日本独自の文字体系も壊されて行きました。
言ってみれば第二次世界大戦で勝った欧米列強の圧力に負けて、日本語を捨てるように強要されて、英語を使うように強制されたような感じです。
唐と新羅から表意文字である漢字を強要されただけではなく、それまでの日本独特の文字である神代文字も消されていきました。
それでも何とか生きながらえた神代文字が、13種類ほど残ったと言われています。
その中でも「秀真傳」を記した「ヲシテ文字」は、表意文字と表音文字が混ざり合った秀逸な文字であったと、国学者の平田篤胤は評しております。