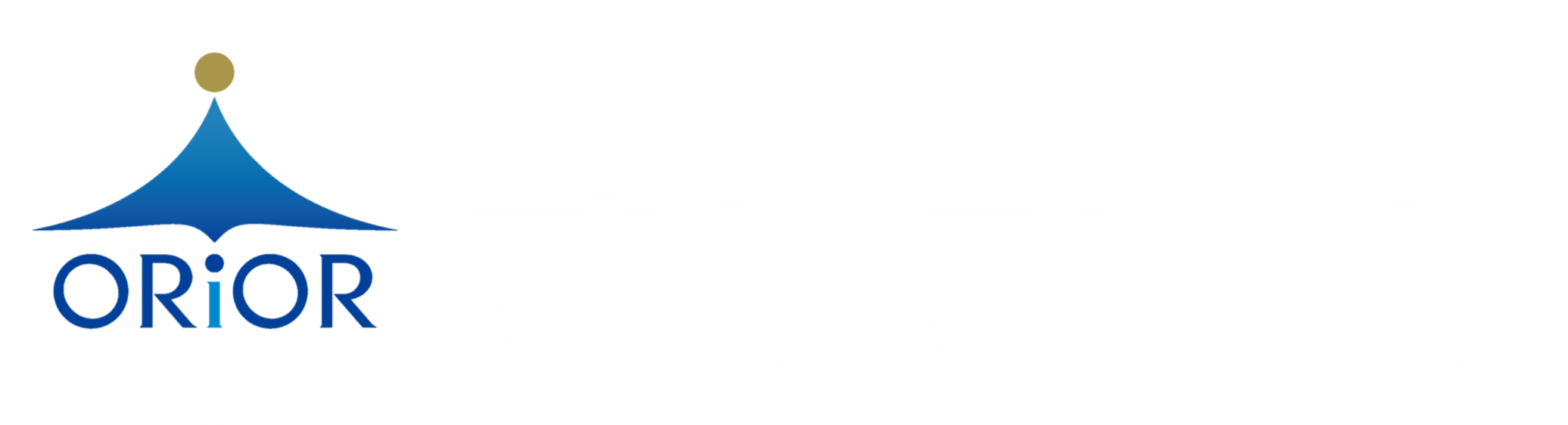さすがに今でもMMT理論を推す人達は少ないかと思いますが、2019年辺りでは色んな政治団体が声高に「素晴らしい理論だ」と叫んでいました。
しかし、この理論一見は難しそうに思いえますが、既に日本では江戸時代に行っていたと言ったら驚かれるでしょうか。
そもそもMMT理論とは「自国通貨で出した国債ならば、インフレが起きていない状況の時には、いくら借金の為の国債を出しても潰れない」と言う理論なのです。
江戸時代、武家が商家などに借金を作り、武士たちが苦しんだ時など(元禄の改鋳1695年、宝永の改鋳1706~11年、元文の改鋳1736年、文政の改鋳、天保の改鋳、安政・万延の改鋳など)幕府は金や銀の含有量を減らし、貨幣の流通量を増やしました。(いわゆる改鋳ということです)
その途端、たちまち貨幣の信用が下がり、あっという間に経済はインフレ状態となり悪化しました。
まさに、実体経済に裏付けがない、信用の裏付けがないMMT理論の様なものはあり得ない話です。
借金が帳消しになる訳ではなく、分散されて見え難くなっているだけで、実際は誰かが負担している事に変わりはないのですから、「打ち出の小槌」とはいかないということです。