アリストテレスは「人生の目的は幸福である」と語っています。
彼の教えを受けたアレクサンダー大王は、若くして亡くなりますが、彼が世界帝国を築いた背景には、「人生の目的は幸福になること」と言う積極的な光明思想が流れていたから、広大な地域の人々を幸福にしようと帝国を築いたのかも知れません。
同様に西田幾多郎博士も著書「善の研究」の中で「幸福」について言及しております。
彼は「幸福とは善である。善であることが幸福なのだ」という言い方をしています。
善であると言うことは「人間としての生き方として正しい」と言うことであり、善悪で言えば「悪から遠ざかり、善を選びとる」「悪を押しとどめ、善を推し進める」と言うことになるでしょう。
これはお釈迦様が説いた「止悪修善」という考えとも合致します。
だからと言って「この世では幸福でも、死んでからは地獄で不幸」と言うのでは、かないません。
「この世では、お金持ちになりました。地位も名誉も得ました。その陰で悪い事をして、沢山の人を泣かせました。そして死んだあとは地獄に堕ちました」と言うような幸福論では、虚しさしか残りません。
だからキリスト教では「この世の成功学や幸福論は虚しい」という考え方が根強くあり、「この世で不幸だからこそ、あの世で幸福になる」という考え方も生まれきました。
これはイスラム教にも存在し「この世での迫害や受難や殉教で不幸を味わうと、天国が待ち構えている。補償作用として天国での幸福が待っている」と言う考えにもなっています。
しかし「幸福とは善である」と言う考え方からすれば、「この世で生きていても幸福、死んでからも天国で幸福」が一番良いに決まっています。
だからこそ、「人が喜んでくれる仕事をしてお金持ちになり、その財力と権力を世の中の為に使って幸福になり、この世を去ってからも天国で幸せに暮らしました」と言う流れを求めることが、大切とされているのでしょう。
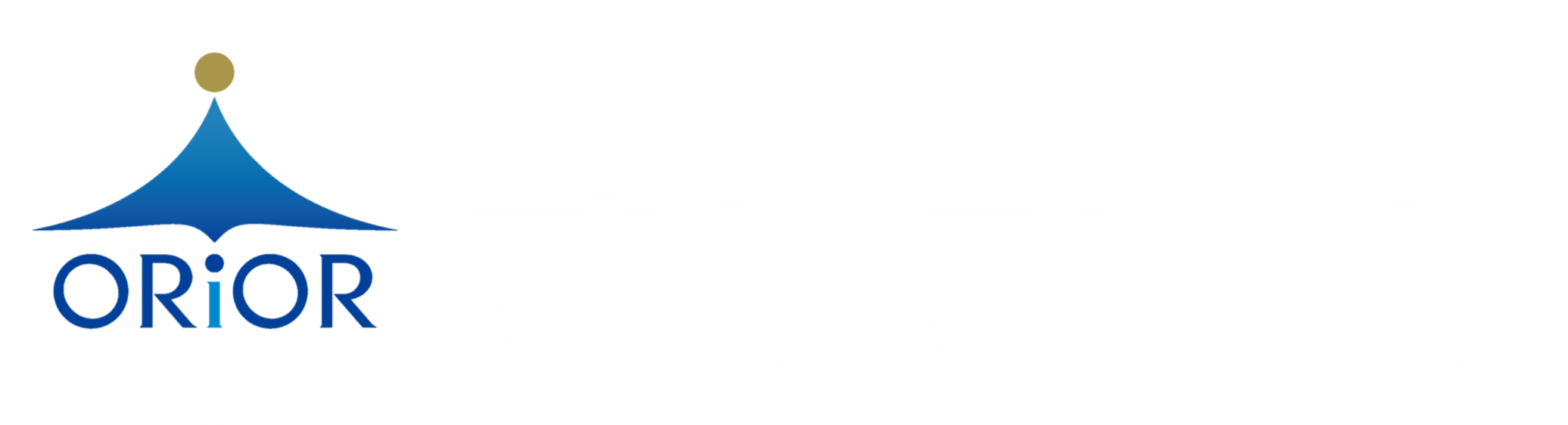

人が喜んでくれる仕事は
自分にとっても喜びですね。
これからもブログで学ばせて
頂きますね
ありがとうございます♪
仰る通りですね!