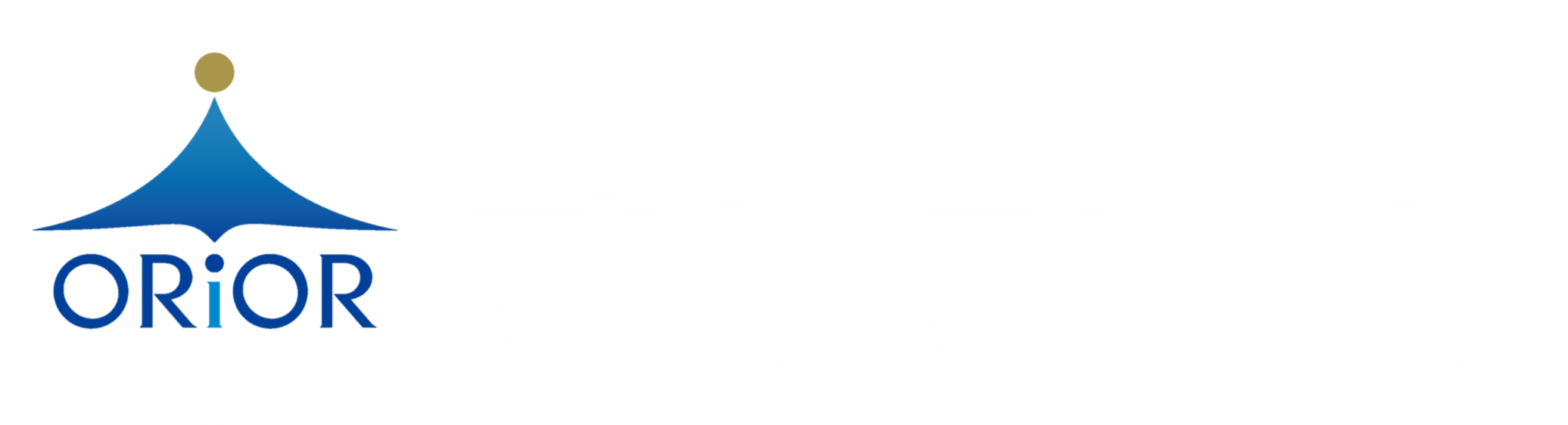「一燈を捧げて暗夜を行く。暗夜を憂うること勿れ。ただ一燈を頼め。」とは、佐藤一斎の『言志晩録』第13条に書かれている言葉です。
「闇を恐れるのではなく、自分の提げているその一燈をこそ頼め。自分の持っているこのランタンの光、一燈を頼りにして、ただただ闇を進め。闇を恐れるな。」というようなことを言っております。
この教えは、儒教でもありながら、キリスト教にも似たところがありますし、他のものでも通用する真理だと思います。
「闇を闇雲に恐れていると、闇に飲み込まれる。自分の中にある『真理』の火を灯せ、さすれば闇は一気に消えて、道が歩きやすくなる。」ということなのですが、その「真理の火」が分からないが為に、多くの人達が道に迷っています。
「真理の火」は、古今東西の賢人や哲人が、言葉を変えて仰っているのですが、現代人の多くは言葉面だけ捉えて、その奥にある深遠な知恵を理解しようとしません。
「情けは人の為ならず」と言われると、「他人に情けを掛けてはいけない。甘やかすとろくな人間にならない。」と捉えている方が、そこそこの数いらっしゃると聞いて驚いたことがあります。
「他人に情けを掛けるのは、周り廻って自分に帰ってくるから、他人の為ではないのだよ。」という事を教えようとして、先人たちは言葉を綴ったのですが、今では多くの方にとって意味がすり替わって来てしまっています。
こういうことが多々あるので、自分の目で足でシッカリと調べて行く事も「真理の火」を学ぶ上では大切な事です。