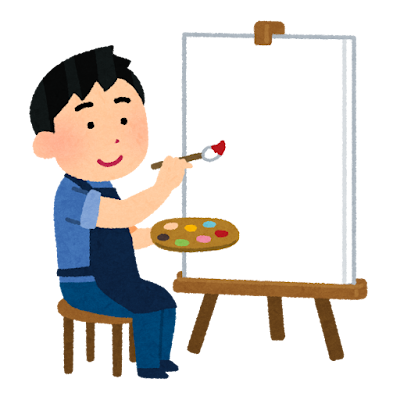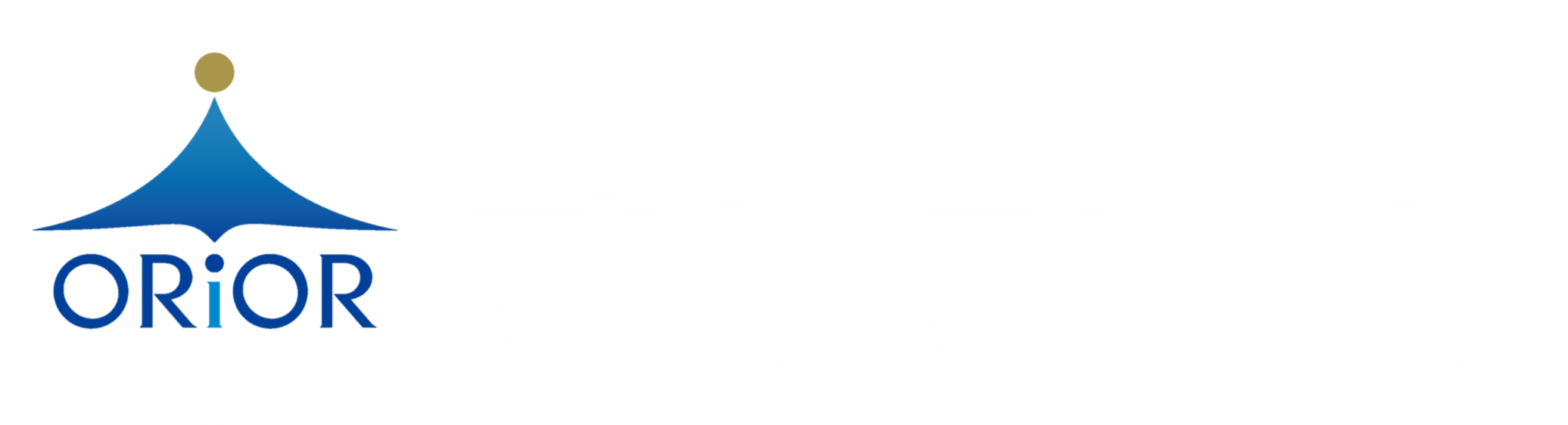執筆者 orior | 2026年02月12日 | カウンセリング
例えば、あなたをガッカリさせる言葉や、あなたのやる気を無くす言葉を投げかけられたら、あなたはどうしますか?その言葉で「一日中悩むのも自由」「一年悩むのも自由」「一生悩むのも自由」です。でも、「悩まない自由」もあります。あなたの心を踏みにじる言葉を投げた人も、本心から言ったわけではないかも知れません。たまたま、その日は朝から悪いことが立て続けに起きていて、普段はそんな事を言わない人なのに、目の前にいたあなたに、つい攻めるようなこと言ってしまったかも知れません。あなたも同じような経験があるように、彼らにもそう言う事が起きたとしても不思議で...

執筆者 orior | 2026年02月11日 | 雑記帳
「口(くち)」が濁れば「愚痴(ぐち)」になります。口が濁るとは、言葉が汚れること。あなたから発せられた愚痴は、ゴミのように受け手の心に届けられます。「意思」が濁れば「意地」になります。自分の意志が濁るとは、自分の欲が執着に変わること。食欲、睡眠欲、性欲など基本的な欲がないと人は滅亡してしまうし、成長したいという欲がないと、人は進化も進歩も無くなります。しかし、欲が過ぎて執着に変わると、執着は自分の心を頑なにしてしまいます。「それが欲しい」と意地を張り、周りの人を傷つけてしまいます。「徳」が濁ると「毒」になります。他人に良かれと思ってし...

執筆者 orior | 2026年02月10日 | カウンセリング
自分の人生を振り返った時に「どうして自分の人生は、こんなに困難で苦しい事ばかりが続くのだろう。」と思う人もいることでしょう。しかし、そうした苦難困難ばかりが続く人は「神様から期待」されている人なのだと、私は思うのです。期待されているからこそ「そのくらいの苦しみは乗り越えられるだろう」「その程度では負けないだろう」と試されているのではないでしょうか。その試しを乗り越えることで、「どんどんと成長して、多くの人を救ってくれる私の手足となる人だ」と神様が見込んだからこそ、「これでもか!これでもか!」と辛いことが降り注いで来ます。苦しみが多い人...

執筆者 orior | 2026年02月09日 | カウンセリング
努力の天才は、「いいわけ」を語りません。自分で発奮し、自分で自分を励まします。「他の人に任せたらダメだ」「自分がやらなくてどうする」と、自分を鼓舞します。その時に、体調のせいにしたり、天気のせいにしたり、家族のせいにしたり、景気のせいにしたり、色々な環境のせいにしたりしません。そうしているうちに「やるきが上がってくる」ので、再び努力精進します。このように努力の天才は、どんな過酷な環境の中でも、自家発電するように「活力」を自分自身に与えて続けて行きます。こうした人こそ、天才と呼ぶに相応しい人だと私は思います。...
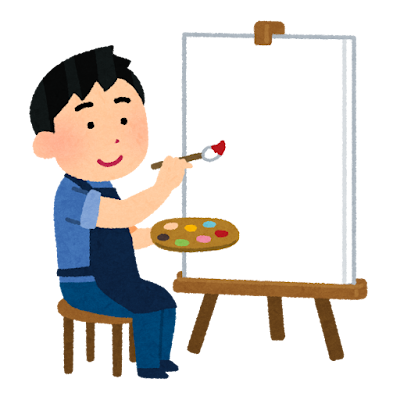
執筆者 orior | 2026年02月08日 | カウンセリング
「なさけない。こんな事も出来ないなんて…」「また同じことで叱られた。自分はダメだなぁ…」こんな思いは、人生の中で何度も数え切れないくらいやって来ます。その都度、反省する事はもちろん大切ですが、反省したら「クヨクヨしない!」という事も大切です。あなたは、自分の運命を決める力を持っています。あなたは、自分が信じる通りの人になっていきます。心の中で思い続ける自分の姿が、成功の絵となって現れて来ます。だから努力精進は、その絵を描くための絵筆です。勇気は、その絵を描くためのキャンバスです。勇気がなければ、そもそも絵筆で絵を描く事も出来ません。勇...