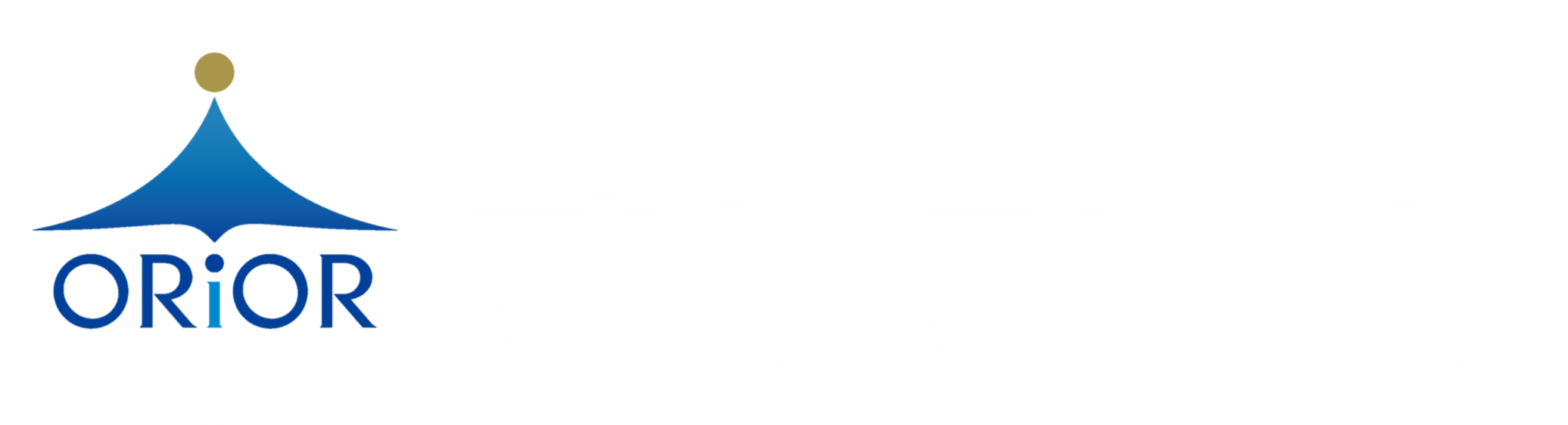執筆者 orior | 2026年02月07日 | カウンセリング
毎日毎日「今日一日で終わるかもしれない」と思いながら「この一日を周りの人のため、世の中のお役に立てるために使いたい」という気持ち、あるいは「自分の持っている力を全て使い切りたい」と思って生きている人は、3年も経つと全くの別人になっていることが起きます。たった3年と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、3年間毎日持続する力は、とてつもない成長を促します。1,000日程度の毎日の持続力で、人は劇的に変わることができます。毎日、毎週、毎月の変化は微々たるものかも知れませんが、その蓄積は久しぶりに会った方にはしっかりと認識できます。私は、そう...

執筆者 orior | 2026年02月06日 | カウンセリング
今の世の中は「いいね」や「フォロワー」が沢山いると、「あの人は凄い!」とかいわれる時代です。しかし、これは現代に限ったことではなく、人間が集団生活をしてきた頃からある「本能」ともいえます。多くの人に信用信頼されないで、人の上に立つ人が居ないように、人に愛されないで成功者となった人も居ないのです。現代も「どれだけ多くの人に愛されているのか」で、自分の価値が決まると言っても過言ではないでしょう。この言葉が真理かどうかは、その逆を想像してみればお分かりになるはずです。「周りの人に嫌われている人がリーダーになる」ということは、何処かのような血...

執筆者 orior | 2026年02月05日 | カウンセリング
天真爛漫と聞くと、「ちょっと何処か抜けている明るい人」と言うイメージを持つ方もいらっしゃるかも知れませんね。それ以前に「天真爛漫(てんしんらんまん)」という言葉を、聞いたことがない方もいらっしゃるかも知れません。今では死語になりつつある「天真爛漫」ですが、あなたの周りに「あの人そうかも」という人がいらっしゃれば、その方はラッキーです。何故なら、天真爛漫な方が側にいると、あなた自身も運気が上がる可能性が大きいからです。では、どんな方が天真爛漫かと言うと、飾り気がなく、生地のまま美しい心で「他の人に対して優しくしよう」とか「自分自身に対し...

執筆者 orior | 2026年02月04日 | 雑記帳
生物の起源を求めると、LUCA(ルカ:Last Universal Common Ancestor)にたどり着きます。ルカは、約40億年前に生息していた地球上の全生物の「最終共通祖先」とされています。といっても最初の生命というわけではなく、多様な初期生物から生き残った唯一の系統で、高温・無酸素の深海熱水噴出孔のような極限環境で生息していた単細胞の微生物と考えられています。...

執筆者 orior | 2026年02月03日 | カウンセリング
「貴方にしか出来ないこと」を考えてみたことはありますか?それは、仕事が出来ることでもない。芸術的センスを発揮することでもない。誰かの上に立ってリーダーとして頑張ることでもない。誰かの真似をして「成功者」として呼ばれることでもない。貴方が今まで歩いてきた人生、辛くて苦しくて涙で泣き腫らした日々、諦めかけた夜…その全ての経験が「貴方自身そのもの」。自分の人生を一生懸命に生きてきた貴方だから、貴方の経験で、貴方の声で、貴方の想いで、救われる人が世界中の何処かに必ず居るはずです。だから貴方の人生を、ありのままに生きることで、それだけでもう誰か...