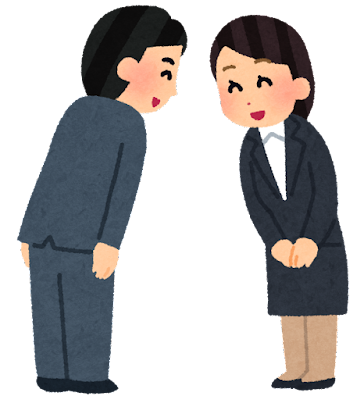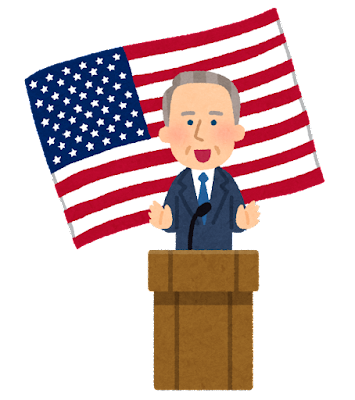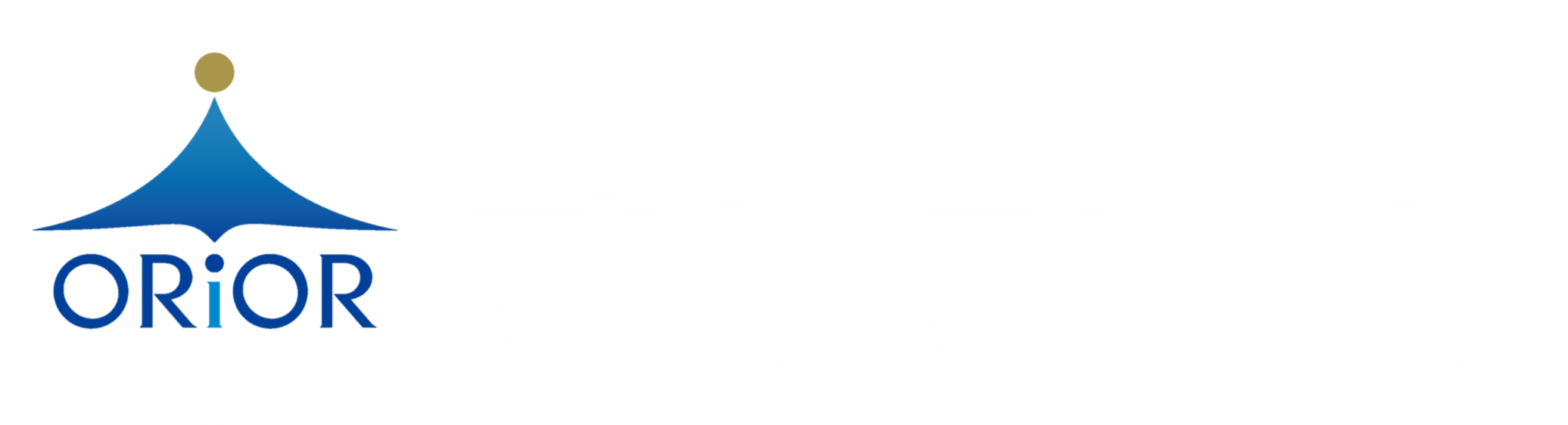執筆者 西村 | 2025年08月12日 | 雑記帳
ピーターの法則とは、能力主義の階級社会において、有能さを発揮できていた地位から出世したとたん、無能になってしまうため、組織全体に無能な人間があふれてしまう法則のことを指します。例えば、営業マンとして優秀な平社員を課長や部長に抜擢したとたんに、管理職に向いてない事が露呈して、課内部内がおかしくなるだけではなく、優秀な営業マンがいなくなった分、、営業成績も落ちて、会社組織全体が下がってしまう事があったりします。これは「能力主義が行き着いた闇」と米国では揶揄されますが、実際のところ仕事能力と管理能力を分けて考えていないから起きる事であること...

執筆者 西村 | 2025年08月11日 | 雑記帳
子供達に、ピアノや水泳、書道や学習塾に通わせる親御さんたちは多いですが、本当に子供達の将来を思うのであれば「克己心」を持たせる事に、お金と時間を費やすことをお勧めいたします。克己心とは、自分が窮地に陥っても、自分自身で自分を奮い立たせる心持ちのことを言います。即ち、克己心があれば、どんな苦しみや悲しみの中にあっても、挫けず諦めずにまた立ち上がって前に進むことが出来ます。克己心がないと、苦難困難が現れて来ると逃げたくなり、自分の成長からどんどん遠ざかって行きます。そうした人物は事を成すことが出来ず、自分自身にも自信が持てなくなってしまい...

執筆者 西村 | 2025年08月10日 | カウンセリング
顔もスタイルも素晴らしい、完璧主義の美男美女は「世界中の恋人」のようになって、多くの人達にモテるでしょう。それを目指して、整形や美容にお金と時間を掛ける人達もいます。しかし、結婚できる相手は特別な国でない限り一人と決まっています。「素晴らしい相手をゲットする為に、自分を磨いている」と言う方もいらっしゃるかと思いますが、そういう方でも同性の人達に嫉妬されたり、言われのない噂話を流されたりして、苦労している人達もいらっしゃいます。完璧だと思われる美男美女も、「おっちょこちょい」だとか「お人好し」とか「天然キャラ」であると愛されやすくなりま...
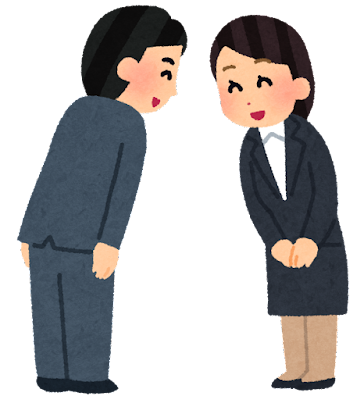
執筆者 西村 | 2025年08月09日 | カウンセリング
「自分は非凡だ。才能がある。」と思っている人は、謙虚にもなれないし、感謝も出来ません。しかし、努力を重ね、平凡な澱みから這い上がってきた人は、他人に対して無関心でいられません。機会があれば、「今、平凡の澱みで苦しんでいる人を助けたい。」と常々思っています。こうした人達が貴人であり、努力精進する人達を助けてくれる救世主となります。この貴人と出会う為には、コツが必要です。先ずは「夢や希望を持って、自分の使命を生きようと、真剣に努力していること」が大切です。「どこかで良い人と出会えたらなぁ」とか「棚ぼたで良いことが起きないかなぁ」と思ってい...
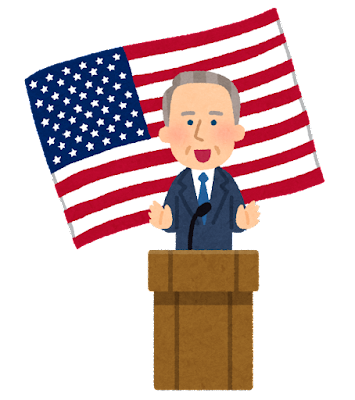
執筆者 西村 | 2025年08月08日 | 雑記帳
欠点や弱点は誰にでもあるものですが、そこを直そうと努力するよりは「長所を伸ばした方が良い」と言う言葉を、皆様も聞いたことがあるかと思います。これは実際の著名人たちも、意識的にやったり、無意識でそうなっている場合もあります。例えば、米国のケネディー大統領はハーバード大学の卒業生ですが、入学の際は成績があまり良くなくて、面接で何とかギリギリ入れたそうです。彼は勉強の成績はイマイチでしたが、高校でのリーダーシップと、何とも言えない人間的魅力を面接官が感じたようで、合格出来たのです。また彼は右脚左脚の長さが少し違っていたため、脚を引き摺ってし...