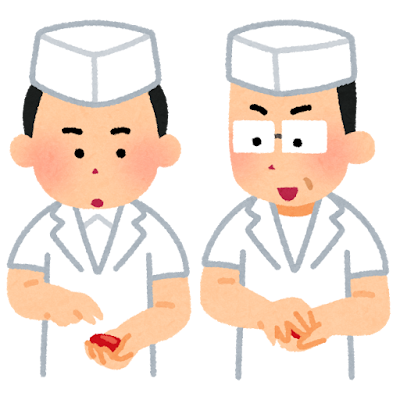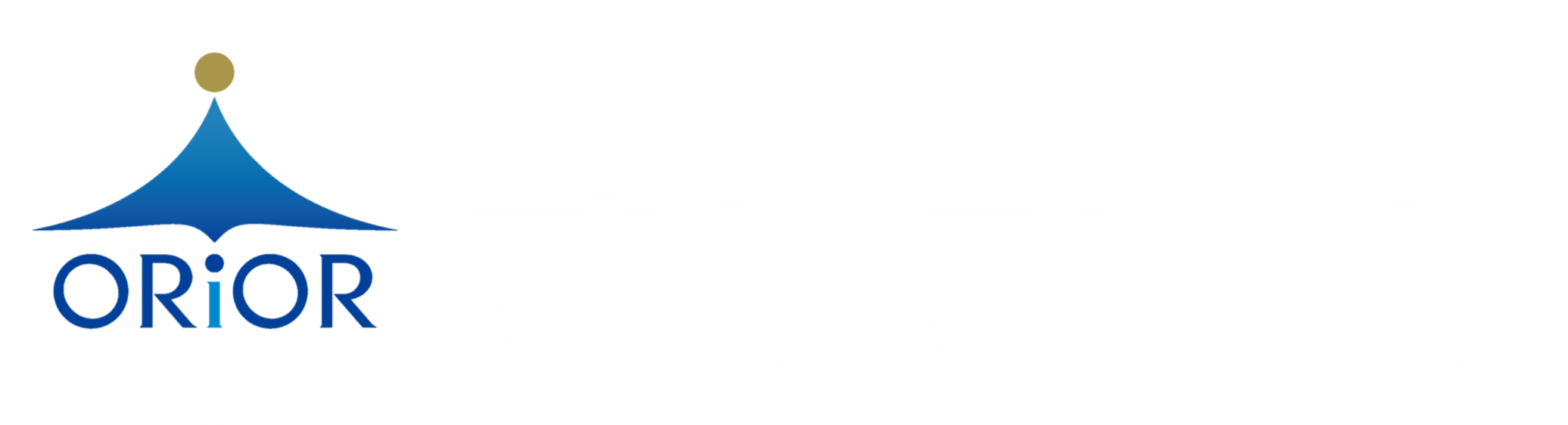執筆者 orior | 2026年02月11日 | 雑記帳
「口(くち)」が濁れば「愚痴(ぐち)」になります。口が濁るとは、言葉が汚れること。あなたから発せられた愚痴は、ゴミのように受け手の心に届けられます。「意思」が濁れば「意地」になります。自分の意志が濁るとは、自分の欲が執着に変わること。食欲、睡眠欲、性欲など基本的な欲がないと人は滅亡してしまうし、成長したいという欲がないと、人は進化も進歩も無くなります。しかし、欲が過ぎて執着に変わると、執着は自分の心を頑なにしてしまいます。「それが欲しい」と意地を張り、周りの人を傷つけてしまいます。「徳」が濁ると「毒」になります。他人に良かれと思ってし...

執筆者 orior | 2026年02月04日 | 雑記帳
生物の起源を求めると、LUCA(ルカ:Last Universal Common Ancestor)にたどり着きます。ルカは、約40億年前に生息していた地球上の全生物の「最終共通祖先」とされています。といっても最初の生命というわけではなく、多様な初期生物から生き残った唯一の系統で、高温・無酸素の深海熱水噴出孔のような極限環境で生息していた単細胞の微生物と考えられています。...

執筆者 orior | 2026年01月31日 | 雑記帳
日本列島は、もともとユーラシア大陸の一部でしたが、地殻変動により現在の島国となりました。 数億年前まで、長らくアジア大陸の東端に位置し、プレートの沈み込みによって新しい地層(付加体)が継ぎ足されていきました。約2500万年〜1500万年前頃から、...

執筆者 orior | 2026年01月30日 | 雑記帳
皆様はよく、「潜在意識」とか「顕在意識」とかの言葉を使っていらっしゃるかと思います。しかしながら、この考え方はあくまでも心理学上の「仮説」であって、科学的に実証された事が無いことをご存知でしょうか?「潜在意識」や「無意識」の概念は、精神科医のジークムント・フロイトによって確立され、カール・ユングによってさらに発展しました。フロイトは、意識を「意識(顕在意識)」、「前意識」、「無意識(潜在意識)」の3つの領域に分け、特に無意識が行動や感情に大きな影響を与えているとしました。それに対してユングは、フロイトの個人的無意識に加えて、人類共通の...
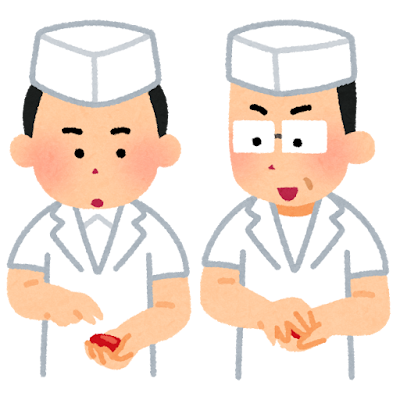
執筆者 orior | 2026年01月29日 | 雑記帳
師匠と言う人達を持っている方々が世の中には、意外と少ないような気がします。何か習い事をしている方には、先生や師匠と呼べる人がいらっしゃるとは思いますが、その辺の人を捕まえて「あなたに師匠と呼べる方はいらっしゃいますか?」と訊いたら、どれだけの方が「いる!」と答えるでしょうか?3人に1人いたら凄いことだと思いますが、おそらくは5人に1人くらいの割合、つまり20%程度の人に師匠がいるという回答が得られる気がします。少し調べてみたところ、職場においてメンター(指導者・師匠)を持っている従業員は、全体の約40%であるという調査結果があります。...

執筆者 orior | 2026年01月21日 | 雑記帳
日本神道は、縄文時代以前から日本に根付き、浸透して行きました。鳥居は日本神道の象徴とされ、その土地を日本中央政府(色々な豪族を束ねた部族)が支配した場合に、半ば強制的に設置したとされています。そこに、飛鳥時代になり唐(中国大陸)から仏教が伝わり、その教えの高度さに日本神道は圧倒されたようです。それが証拠に、聖徳太子は仏教を国教とすべく積極的に動きました。日本が朝鮮半島に何度も攻めたことも、日本神道を大陸に広めるために断行され、鳥居を建てることが目的でしたが、ことごとく失敗しました。第二次世界大戦においても、日本が勝てば世界中に鳥居が建...