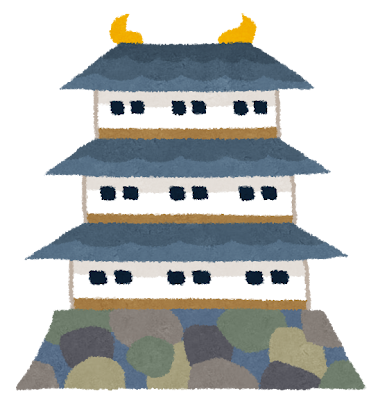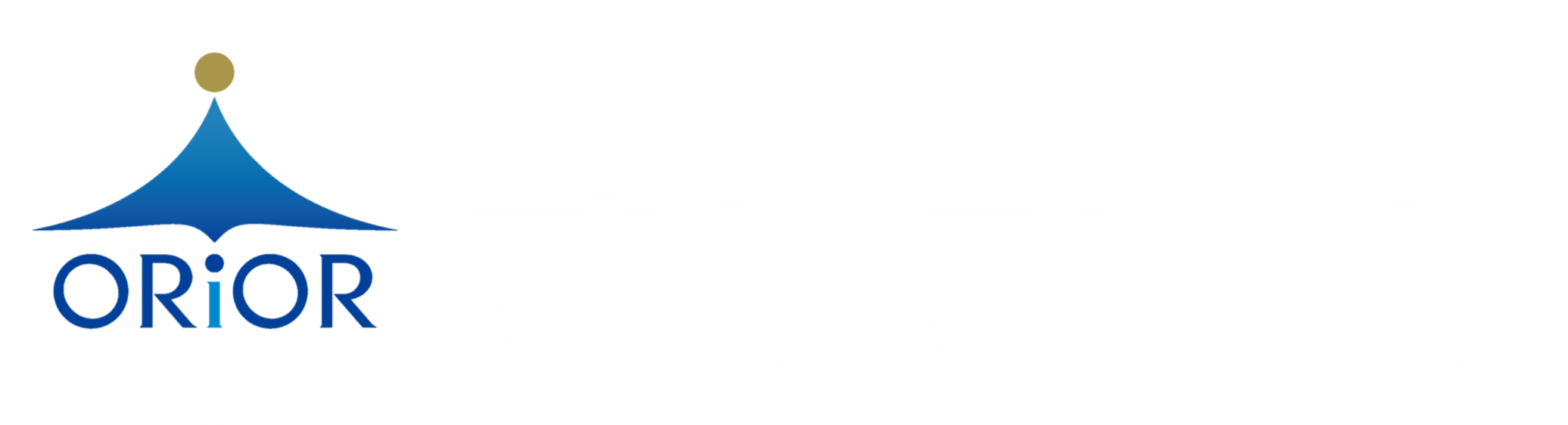執筆者 orior | 2026年01月20日 | 雑記帳
皆様は仏教の中に修験道が入っている感じがしているかと思いますが、実際には修験道は役小角が開祖とされる仙人系の「肉体中心修行」とされているので、純粋な仏教とは分離されるべきです。修験道や山伏などの仙人系は、中国のヨガ系から来ており、仙人道ともいいます。従って、精神修行を主にする仏教と修験道、仙人道は明らかにその修行の趣旨が違うことがわかります。また、武道の中でも修験道、仙人道を核にしているものも多く存在しております。もちろん、仏教系の精神修行を大切にしている武道もありますが、だいぶ少なくなってきている感じは否めません。仙人道、修験道は「...

執筆者 orior | 2026年01月18日 | 雑記帳
第三十三代推古天皇は女性天皇でした。彼女は聖徳太子の父である、第三十一代用明天皇とは兄妹になります。推古天皇の成した政(まつりごと)の成果は少ないですが、聖徳太子を摂政的な立場に置いたことで、日本は「言霊の幸う国」になったと云われています。推古天皇の夫であった敏達天皇は、第三十代天皇でしたが、天皇継承にあたり様々な政治的権力争いが勃発し、常に命を狙われる緊張状態でした。本来は、能力主義で天皇継承していく事が望まれてはいたかも知れませんが、能力主義の場合は「続かない」ということもあって、血脈で跡を継いでいく形の方が「安定性がある」とされ...

執筆者 orior | 2026年01月14日 | 雑記帳
お隣の国は、台湾の事でご立腹のようですが、本格的に日本に手を出した際は、自国が大変なことになる事を充分承知しているので今は「口攻撃」だけに専念していると思われます。日本は例え、核爆弾を首都東京に落とされたとしても、ある程度耐えうるだけの地下防空壕は既に地下鉄網によって整備されています。私達が利用している地下鉄網とは別に、秘密の地下網も造られていう都市伝説もまことしやかに流れています。それゆえ大阪や名古屋や福岡などの人口が集中する大都市圏では、地下鉄網はしっかり整備されています。また、自衛隊も自衛兵器以上の最新兵器も、秘密裏に製造配備さ...

執筆者 orior | 2026年01月10日 | 雑記帳
世界的にナンバーワンになった国は、その軍事力や経済力を背景に、世界での支配力を強めて行こうとします。ナンバーツーは、自分より上の国が邪魔だけれど今は勝てないので、じっと機会を伺いながらも、その力を貯めて行こうとします。世界史的にみても、このナンバーワンとナンバーツーの均衡が崩れ、支配権を奪い合う時、世界大戦が始まります。一番と二番が戦った時には、その様子を三番目はじっと観察し、虎視眈々と自分の伸びて行く未来を見定めます。おそらくは、現代でもこの状況は変わらないので、緊張感が何らかの形で解き放たれた時に、ナンバースリーの天下が現れてくる...

執筆者 orior | 2026年01月07日 | 雑記帳
「絶対零度」という宇宙の法則があることを、皆様はご存知でしょうか?絶対零度とは、℃でいうとマイナス273.15度の温度のことを指します。全ての物質が熱をもたなくなる温度が絶対零度です。つまりは物質の体積がゼロになる瞬間の事を指します。現在では量子力学の発達によって、物質が絶対零度に達した時、その物質は「新たな物資」になるとされています。量子力学的に説明すると、物質は粒の性質と波(波動)の性質を持っております。粒の性質が絶対零度になると動きがなくなり、波動の性質も単調な波動になります。その際に、分子同士の単調な波動が共鳴して、分子が融合...
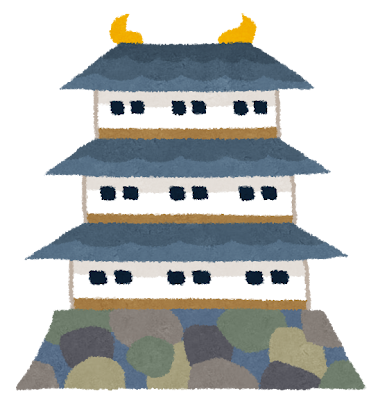
執筆者 orior | 2026年01月06日 | 雑記帳
歴史家の長年の疑問として「豊臣秀吉の中国大返しが可能となったのか?なぜ毛利軍の追撃が無かったのか?」は良く挙げられます。明智光秀によって織田信長が討たれたという知らせが入った直後、直ちに毛利氏と和議を結び、秀吉軍2万の軍勢は備中高松から取って返し、約200キロ離れた山城国山崎の地で光秀軍と戦闘しました。その際に重要な伏線的出来事として「高松城の水攻め」があります。秀吉が、備中高松城を水攻めするための堤防工事で、農民などを動員し、「土嚢一俵につき米一升、銀百文」という高額な報酬を与えることにより、わずか12日間で城の周りの沼地に、高さ7...