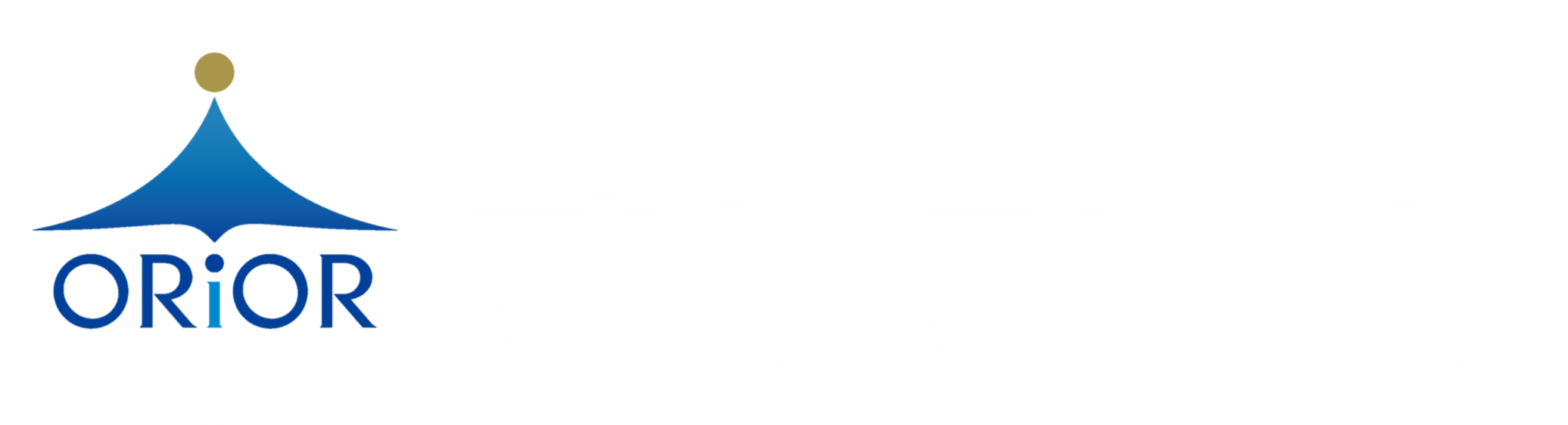執筆者 西村 | 2025年09月05日 | 雑記帳
私達の時間には「相対時間」と「絶対時間」があると言われております。相対時間は、誰にとっても同じように1日24時間であり、マルクスの言う「労働価値説的時間」です。労働価値説とは「単位時間あたりの労働の値打ちは等しく、生産に要する労働量が商品の価値を決める」と言う考え方です。しかし、この思想を否定する学説が、今後は主流となることでしょう。1時間と言う時間は、相対的時間としては誰にとっても同じですが、絶対的時間としては同じではありません。例えば1時間の講義を受けたとしても、「こんな内容のない授業はつまらないな。」と考えていれば、ただ苦痛の時...

執筆者 西村 | 2025年09月04日 | 本当の終活
「悟り」と言うと皆様は、どんなことをイメージするでしょうか。「お坊さんが修行している」とか「坐禅を組んでいるとか」そうした、仏教関係者が何かを精進している姿が想い浮かぶかも知れません。しかし「悟り」は、日常的に私たちの中にもあるとされています。「こう言う態度をとると、他人は喜んでくれる。」とか「人間社会は、こうした原理原則で動いている。」とか、その人が経験や智慧から学んだことが「悟り」のように感じられる時もあります。その感覚は、あながち間違いではないかも知れません。但し、その悟りにも段階があります。仏教ではその段階を「預流(よる)」「...

執筆者 西村 | 2025年09月03日 | 雑記帳
「正念」は「正しく念ずる」と書きます。「正しい念」とはどういう事を指すのでしょう。昨今、引き寄せの法則や与祝など、願いや願望を成就させる方法が多々出ておりますが、これも「念」の一種です。「おもい」は3種あると言われています。先ずは「思い」。これは日々、心の中に直ぐに現れて消える水蒸気のような感じです。例えば「〇〇したいな」「可愛いな」「寂しいな」など一瞬の「おもい」です。次に「想い」があげられます。こちらは先ほどの「思い」よりは固定化して雲のような状態を指すでしょう。「想い出」などのように「あの時のことを鮮明に想い出す」とか、一瞬の思...

執筆者 西村 | 2025年09月02日 | カウンセリング
若い人達は、力の限り、能力の限り、フルパワーでもって自分を表現しようとします。「自分を丸ごと認めてほしい。」と言う表れなのかも知れませんが、これは大きな鯛をドーンとまな板に乗せて「はい、どうぞ。食べて下さい!」と言うようなもので、相手は「どうやって食べろと言うのだ。」と言うことで、戸惑ってしまう事もあります。自分自身を丸ごと差し出しても、相手は食べられないだろうと思えば、刺身にしたり、煮付けにしたりするなど、食べやすいように調理していくと言う考え方も必要となります。エネルギーを強く出すことは出来ても、弱くすることが出来ないと、あなたを...

執筆者 西村 | 2025年09月01日 | カウンセリング
私達は、日々多くの誘惑にさらされて生きています。「この商品は貴女を美しく見せますよ!」「これを使うとあなたの身体は一気に健康になります!」「これを持っていると運気が上がります!」様々な誘いや宣伝文句があるので、ちょっとお金に余裕があると、ついつい購入してしまう事もあります。しかし、大半は「無くても何とかなるもの」なので、後から後悔してしまう事も多々あります。こうした欲を律して行く中で「いかに正しい生活をして行けるのか。」を私達は日々試されているのかも知れません。お酒やタバコ、ギャンブルなども行き過ぎると、良い事はありません。また易や占...