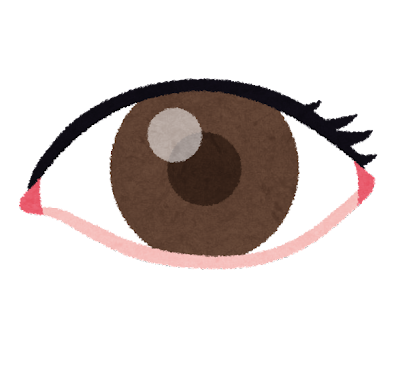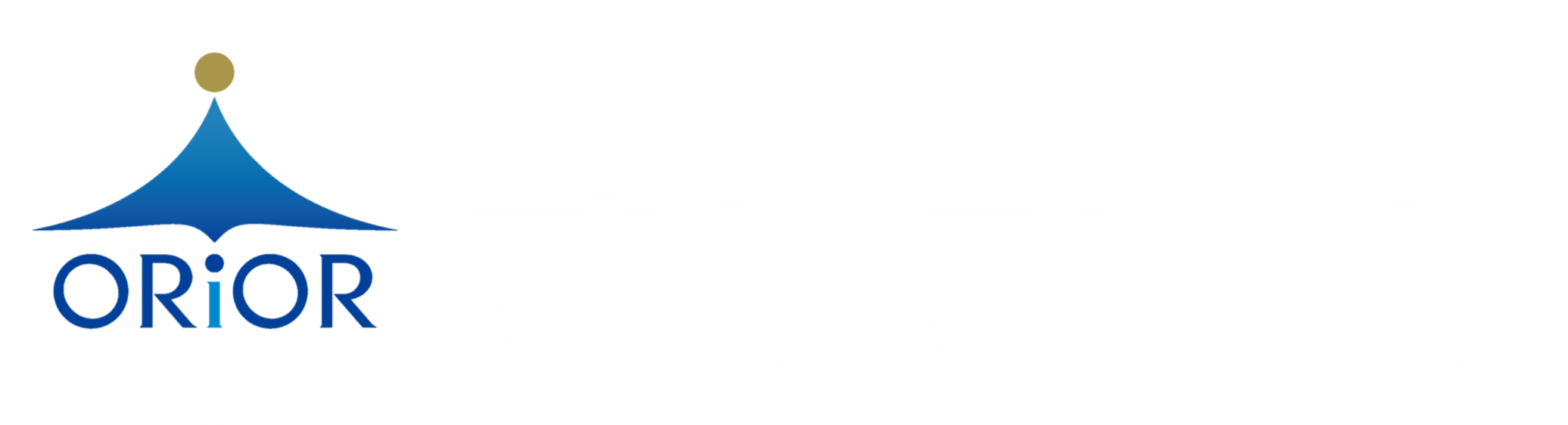執筆者 西村 | 2025年08月07日 | 雑記帳
宮本武蔵は剣豪と知られるので、多くの方がその名前をご存知かと思いますが、彼は柳生新陰流の様な剣の流派は創りませんでした。宮本武蔵は人格者としての一面も持っていたとされますが、弟子を持たず一代で、彼の剣の道は終わりました。何故彼はそれだけの剣の力を持ちながらも、流派を創れなかったのでしょうか。彼には調整能力、すなわちコーディネート能力が欠けていたからだとされています。会社の中でも「仕事は出来るけれど、一匹狼的な人」は何人かいたりします。こうした人は、組織的に物事をこなすよりも、自分で動いて、自分の中だけで完結させる仕事が好きなタイプの方...

執筆者 西村 | 2025年08月04日 | カウンセリング, 雑記帳
超一流と言われる人物の共通点として挙げられるのが「人間観察力」です。人に対する洞察力が低い人は、どうしても他人の能力や性格を見抜けず、良いところまで行っても、何らかの理由で転落してしまう事が往々にしてあります。「孤軍奮闘し会社を大きくしたけれど、信頼していた右腕に裏切られて倒産」と言うお話は、皆様も何処かで聞かれた事があるかと思います。滅多にない話だから、そのように人を介して語り継がれるのでしょうが、実際に被害に遭われた方からお聞きしてみると「何となく違和感はあったけれど、忙しさで無視していた。」とか「怪しい感じはしていたけれど、まさ...

執筆者 西村 | 2025年08月02日 | 雑記帳
「布施(ふせ)」とは、仏教で言うところの「僧侶や僧団に対して物品などの施し」をすることですが、お賽銭やお札を買い求めることも、広義の上では「布施」と言っています。しかし本来は、「人が、自らが大事なものを神や仏に差し出すことで、その執着を断つ修行の一環」として「布施(行)」があったのです。ですのでお釈迦様は、弟子の僧侶に対して「あなた方は物乞いではない。あなた方は実は与えているのだ。布施の機会を与えることで、布施をする人達に大きな愛を与えているのだ。あなた方がお椀を差し出す時、無言のうちに彼らを教え導くことが大事なのだ。与えると言う行為...

執筆者 西村 | 2025年07月30日 | 雑記帳
相談者から七福神の質問をされることが、何故か最近多くなってきました。特に弁財天様が気になる方が多い様で「どう言う謂れの方なのでしょう?」と訊かれるのですが、元々はヒンズー教における「サラスバーティー神だと思われます」と答えています。彼女はヒンズー教における「水と豊穣を司る女神」であり、芸術や学問など「知を司る女神」でもあります。その女神が、日本に仏教伝来の際に伝えられて、神仏習合で弁財天と呼ばれることになったようです。インドでは内陸部が深く、海を知らない人達の方が多いので、「水の神」となると「川の神」とイコールになり、川の神サラスバー...

執筆者 西村 | 2025年07月29日 | 雑記帳
「竜宮城でタイやヒラメの踊りを見物」とは浦島太郎のお話ですが、意外とあるかも知れないと言ったら、皆さんは驚かれることでしょう。実際に誰もが観ることはできないかも知れませんが、ここ静岡県にも竜宮城があると言われています。場所は「三保の松原」静岡市清水区になります。美しい海岸と松原の中に富士山が浮かぶ景勝地です。天の羽衣伝説が残っている場所でもあります。こうした竜宮城があるとされている所は、海や川や湖など水が綺麗な場所が多く、美に関するお仕事をされている方々が良く訪れると聞いております。世界的な有名ブランドの創業者一族が、三保の松原に来ら...
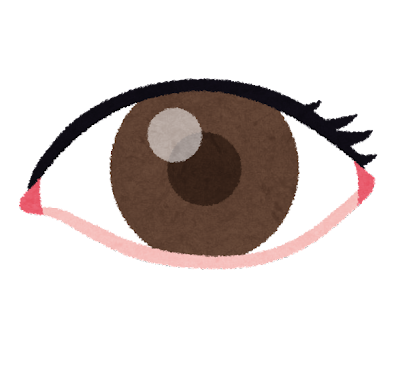
執筆者 西村 | 2025年07月27日 | 雑記帳
皆さんの前に、「明るくて積極的で、夢と希望に目を輝かせている人」がいたとして、その方が過去に病気や失業、離婚や事業の失敗をしていたとしても、そのことをその人に問う人が、どれだけいらっしゃることでしょう。恐らくは「そんな過去のことはどうでも良い。今、そんな暗い過去から立ち上がって頑張ろうとしているのだから、応援してあげよう。」と思うのではないでしょうか。もちろん、その人が投資話を持ちこんだとしたら、過去のことも含めてその人の人物像を調べなければならないこともありますが、過去の失敗に縛られて意気消沈している人には、あなたは投資はしないでし...