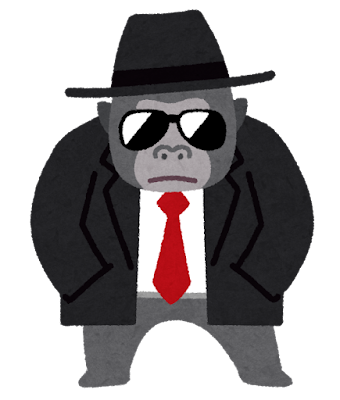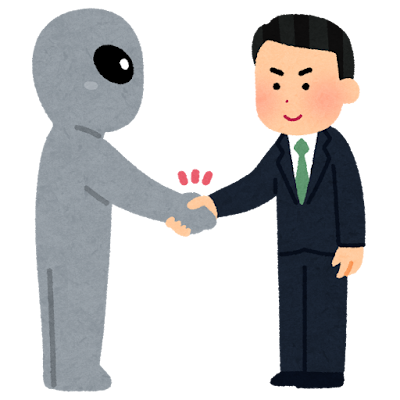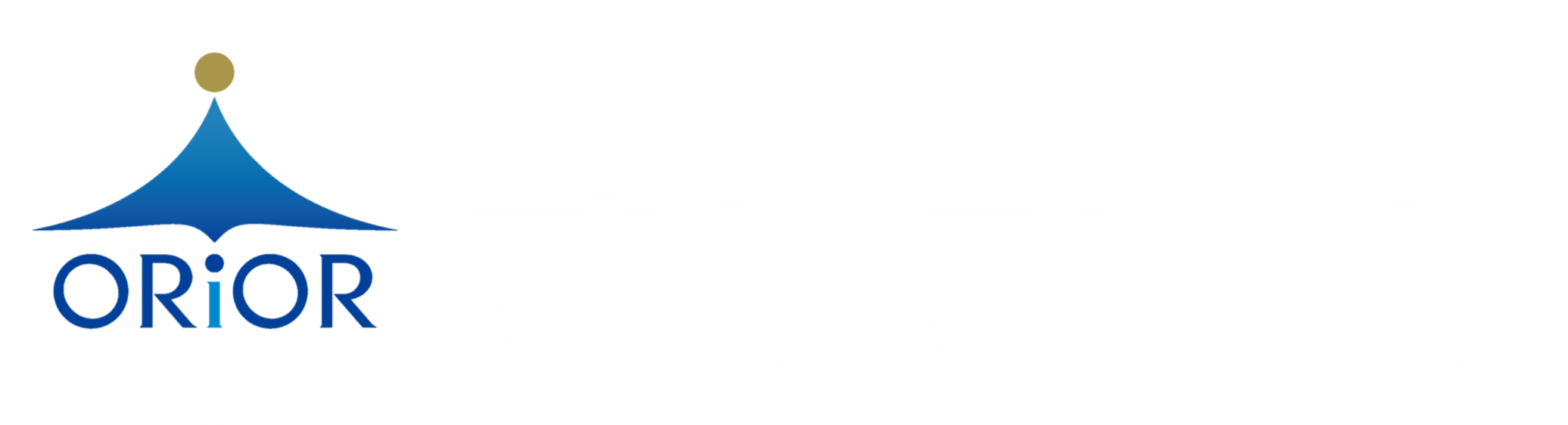執筆者 orior | 2026年01月05日 | 雑記帳
戦国時代の軍師と言われる人たちは、「負ければ終わり」の時代を生きていました。勿論それは軍師に限らず、一兵卒やその地域に暮らしている庶民にまで、命の危険は及びました。それ故に、絶対に負けない策略を創り、将達に与えるのが軍師の役目でした。戦国時代にも軍師は数多くいた事でしょう。皆、孫子の兵法は当然の知識として知っていた事でしょう。ですから勝ち残った軍師は、負けてしまった軍師よりは数段優秀と言えるのです。大将が、リーダーが、軍師の役割を担う事が出来るほど優秀であれば、天下統一も可能かも知れませんが、歴史上そんな大将は一人としていません。つま...

執筆者 orior | 2026年01月02日 | 雑記帳
毎年毎年、「今年は激動の一年となるでしょう」というような予言や予測が出て来ますが、激動でない一年など歴史を見ても明らかですよね。先ずは「私にとって、どんな一年になるのか?を知りたい」という事が、多くの方の本音だと思います。子供達が受験や就職や結婚があったとしても、「自分がそこに、どう関わる年となるのか?」それこそが知りたいのではないかと察します。結論から言いますと「なるようにしかならない!」ということになります。「なんだ!そんなこと分かってるよ!」と言わそうですが、「あなたが想像している範囲内の出来事、若しくは周りがイメージ出来る事柄...

執筆者 orior | 2026年01月01日 | 雑記帳
「阿吽の呼吸」をAIで調べると・・・「阿吽の呼吸(あうんのこきゅう)」とは、言葉がなくてもお互いの気持ちや行動のタイミングがぴったりと一致し、息が合っている状態を意味する慣用句です。元々は仏教用語で、サンスクリット語の「阿(a)」が始まり(口を開けて)、「吽(うん)」が終わり(口を閉じて)を表し、万物の始まりと終わりを象徴する「金剛力士像(仁王像)」や「狛犬」に由来します。...

執筆者 orior | 2025年12月30日 | 雑記帳
日本の戦国時代には「二兵衛(にえい)」と言われる、2人の軍師がいました。一人は竹中半兵衛、もう一人は大河ドラマにもなった黒田官兵衛です。二人とも豊臣秀吉に仕えた軍師でしたが、竹中半兵衛の方が少し先輩格にあたります。ただ、黒田官兵衛の方は秀吉を怖がらせた人でもあったようで、秀吉は「わしの後は、若しかしたらアイツに天下を取られるかもしれん。あまり大きな領地や部下を与えたら、反旗をひるがえすかもしれん。」と言って恐れたというような話が残っています。中国の漢の時代に、劉邦が「韓信にやられるのではないか。」と怖がっていたのと、同じ感じを受けたの...
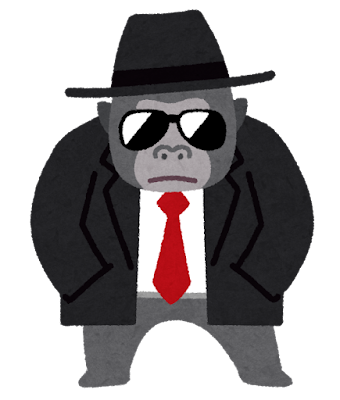
執筆者 orior | 2025年12月29日 | 雑記帳
渡部昇一氏が「息子が大学に入ったら、映画『ゴットファーザー』を観させなさい。」と著者「自分の品格」で書かれていたように、厳しい社会の中で生き抜く為には、ゴットファーザーのような「判断力」がどうしても必要となります。ゴットファはイタリア系マフィアのボスで、いわゆる裏社会で生きながら、一種の権力を持って表社会も動かしていました。その中で「ファミリー」と呼ばれる家族的な組織において、約束を違えたり、反抗するようなことをしたり、裏切った者は消されていくことがありました。そこには当然、それまでの様々な情が絡んでくるので、その部分を考えた上で判断...
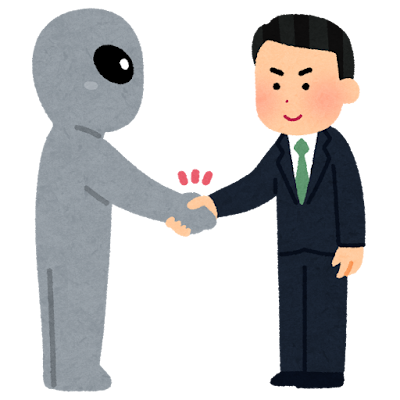
執筆者 orior | 2025年12月27日 | 雑記帳
人の上に立てば立つほど「危機管理能力」を問われてきます。物事が順調に進んでいる時に、リーダーはあまり必要ないのですが、外部の環境が変わったり、予想しない様なことが起きたりした時、要するに「マニュアルに無いような事が起きた時に、どうしたらよいのか?」と言う時こそ、危機管理能力が問われてきます。そういう時に、見事に難題を切り抜けられるような人は「帝王学」を身につけていると言えるでしょう。何事もなかったかのように、普段通りの形にスッと戻していけるようなタイプの人は、人の上に立つべき人です。これには、常日頃の関心の深さが関係しており、色々な事...