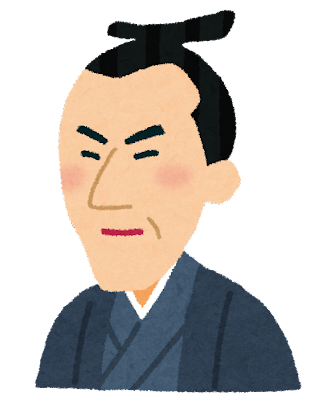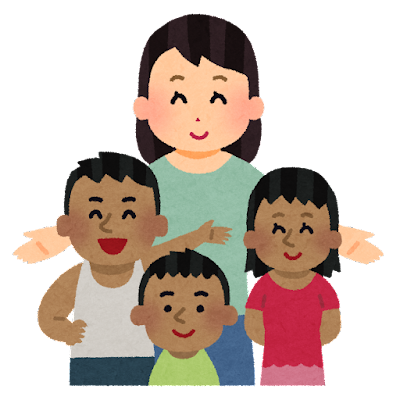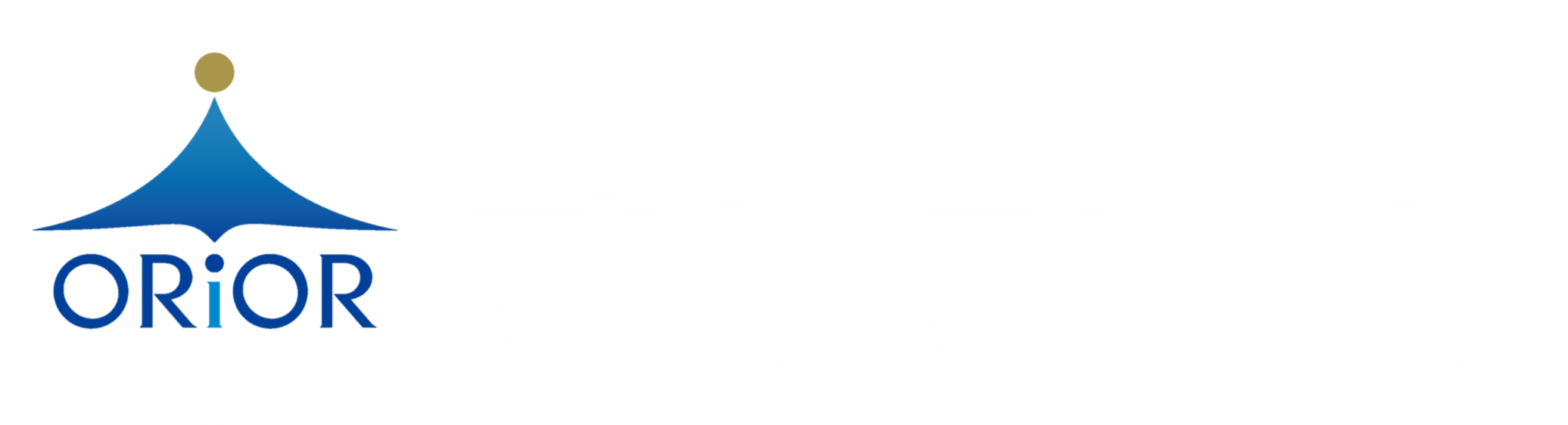執筆者 西村 | 2025年10月16日 | 雑記帳
幕末に生きた佐藤一斎は、朱子学の林家の林述斎に入門して、やがて塾頭になり、『重職心得箇条』と言うものを書いています。これは重役の心得のようなもので、元総理大臣だった小泉純一郎も様々な人に配っていたそうです。佐藤一斎の教えとしては「陽朱陰王」つまり、表は「朱子学」で、裏側は王陽明の「陽明学」です。表側では、幕府の正統な学問である朱子学を教えていたものの、実際は裏に陽明学を忍ばせて教えており「本当は、そちらの方が中心的な考え方だった」と云われています。そのため、その教えを受けた人の中に陽明学が流れ込んで行っているのです。そういった意味で佐...

執筆者 西村 | 2025年10月14日 | 雑記帳
「絶体絶命の時に、退路を絶って戦いに臨む」これを『背水の陣』と言いますが、これは紀元前3世紀頃に中国・前漢初期に活躍した『韓信』が編み出した戦術と云われています。韓信は相手が『孫子の兵法』を勉強している事を逆手に取り、「川を背にして陣を敷くと、敵に攻められたら全滅する」ということで、相手が油断して攻めてくるだろうから、その油断を突く戦いを行いました。韓信は、自分の兵のうち2,000人を割いて、相手の後ろの方に回り込ませて、挟み撃ちにしました。油断していた敵軍は慌てふためき、前後どっちと戦ったら良いのか、どっちに逃げて良いか分からなくな...
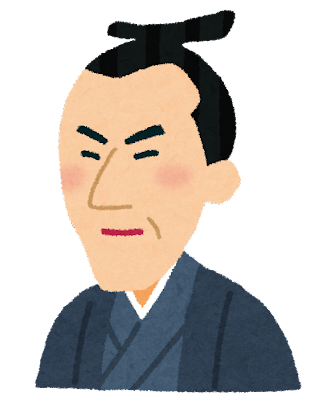
執筆者 西村 | 2025年10月13日 | 雑記帳
佐藤一斎先生についてはブログに書かせていただくのは、これで2度目になるかと思います。彼は幕末に生まれた儒学者で、今の東大の基となった昌平黌(昌平坂学問所)の教授であり、各諸大名や江戸に留学に来ていた諸藩の優秀な武士などに、朱子学や陽明学を教えていました。その門弟は3,000人とも6,000人とも云われ、彼の弟子、孫弟子、ひ孫弟子には、佐久間象山、横井小楠、吉田松陰、勝海舟、坂本龍馬、橋本左内、久坂玄瑞、木戸孝允、高杉晋作、伊藤博文、井上馨、山縣有朋など、錚々たる明治の志士達が名を連ねています。また、明治維新の二大書籍として、福沢諭吉の...

執筆者 西村 | 2025年10月12日 | 雑記帳
「お金持ちから、お金を取って、お金のないところにバラ撒けば、平均的にそこそこ裕福になって良いじゃない。」と言うような感じで、考えている方が、日本には結構多いようです。これは一種の社会主義的考え方であり、国家が累進課税を強化していくことは、社会主義の強化に他なりません。「社会保障と税の一体化」と言うと、非常に良いことのように聞こえ「社会福祉と一体化して、老後の面倒を全て見てくれるなら、いくらでもお金持ちからお金を取っても良い。」という感じにも聞こえてしまいます。しかし、日本ではビル・ゲイツのような大富豪が出ない状態でありながら、そこまで...

執筆者 西村 | 2025年10月10日 | 雑記帳
2012年に公開された映画「天地明察」では、江戸時代に碁打ちだった主人公が暦を作る話ですが、知人として出て来る数学者の関孝和は世界的にみても「凄い人」でした。彼は、世界で最も早く行列式の概念を提案し、微分積分に当たるようなものを独自で作っていたと言われています。また暦の作成に際して、正131072角形から円周率を、小数点第11位まで算出するなど「和算」の発展にも大きく貢献しました。また、歴史でも習った関ヶ原合戦では、東西合わせて約20万人もの大軍が戦っています。これは「当時では世界最大の戦争だろう」と言われていますし、その時に使われた...
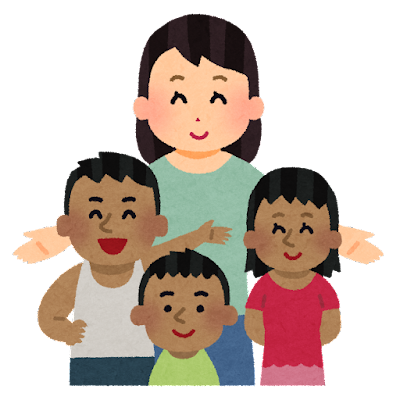
執筆者 西村 | 2025年10月09日 | 雑記帳
三島由紀夫氏が自決してから55年が経とうとしています。彼は東大法学部を卒業して、大蔵省にも入省したくらいのエリートだったのに、「どうして自衛隊基地で自決することになったのか?」いいままで様々な人達が考察してきました。瀬戸内寂聴さんは、2020年に放送されたNHKの番組内で「三島由紀夫氏は、川端康成氏がノーベル賞を取ったので嫉妬して自決したのではないか。」という様に語りました。流石に、この瀬戸内寂聴さんの言葉は、「日本文学を支えてきた先人に対する礼がなっていない。あなたは何様のつもりで言っているのだろう。」と憤りを感じた事を覚えておりま...